物語を楽しみながら、自然な英語表現を学んでみませんか?
このブログでは、短編小説を通して、ネイティブが使うリアルな英語をやさしく解説しています。
キャラ紹介
Prologue: A Normal Evening in Japan, and a Strange App


Yuki opened the front door and stepped inside.
ユキは玄関の扉を開け、中へと足を踏み入れた。
なぜ “step” を使うの? “walk” や “go” じゃダメなの?
たしかに「中に入る」だけなら “walked inside” や “went inside” でも意味は通じます。
でも “stepped inside” は、その場にそっと一歩足を踏み入れるような、控えめで慎重な動作を表します。
つまり、「玄関を開けて中へ入る最初の一歩」を強調しており、静けさやためらい、緊張感などもにじませることができるのです。
“I’m home” she said softly, though she knew her parents were busy.
「ただいま」とユキはそっと言った。両親が忙しいことは分かっていたけれど…
“I’m home” って、「家にいる」って意味だけ? それだけじゃないの?
日本語の「ただいま」と同じく、英語の “I’m home” にも基本的に感情がこもっています。
英語は一見ストレートな言語に見えますが、感情は言葉の選び方や文のつなぎ方で、さりげなく伝えることが多いもの。
たとえばこの文の “though”(~だけど)や “softly”(そっと)は、ユキが両親が忙しいと知りながらも、静かに声をかけた気持ちをやわらかく表しています。
Her father was working in the study, and her mother was probably in the kitchen.
彼女の父は書斎で仕事をしていて、母はたぶん台所にいた。
「仕事をしている」なら現在進行形じゃないの?どうして過去形なの?
これは物語が過去形で語られているからなんです。
英語の小説では、読者が過去の出来事を追体験できるように、時制を過去にそろえるのが基本です。
日本語は時制があいまいでも自然ですが、英語では統一された時制でスムーズに読ませることが大切なんです。
She slipped off her shoes and walked upstairs to her room.
彼女は靴を脱いで、階段を上って自分の部屋へ向かった。
It was already dark outside, and the streetlights shone through her window.
外はすでに暗くなっていて、街灯の光が彼女の窓から差し込んでいた。
Yuki placed her bag on the floor and stretched her arms.
ユキはカバンを床に置いて、腕を伸ばした。
It had been a long day at university. Not too exciting, but not bad either.
今日は大学で長い一日だった。特に面白かったわけじゃないけれど、悪くもなかった。
今さらだけどなぜIt構文を使うの?
上記のようなIt構文は、その日の出来事や状況を客観的にふわっと伝えるときによく使われます。
ただし、文脈やトーンによっては、感情がにじむこともあります。
たとえば “It was amazing.” という表現には、控えめな感動から興奮まで、ニュアンスの幅があります。
英語では、感情をストレートに出さず、少し距離を置いて伝える傾向があり、このIt構文もまた、感情を包み込んでやさしく届ける「ことばのクッション」のような役割を果たしているのです。
She picked up her phone and checked the screen, planning to scroll through social media for a few minutes before taking a shower.
彼女は電話を手に取り、画面を確認した。シャワーを浴びる前に、数分だけSNSをスクロールしようと考えていた。
But something caught her eye.
しかし、何かが彼女の目を引いた。
caught her eye は「(注意・興味を)引く」「目に留まる」という慣用表現です。
“…Huh? What’s this?”
…ん?これ何だ?
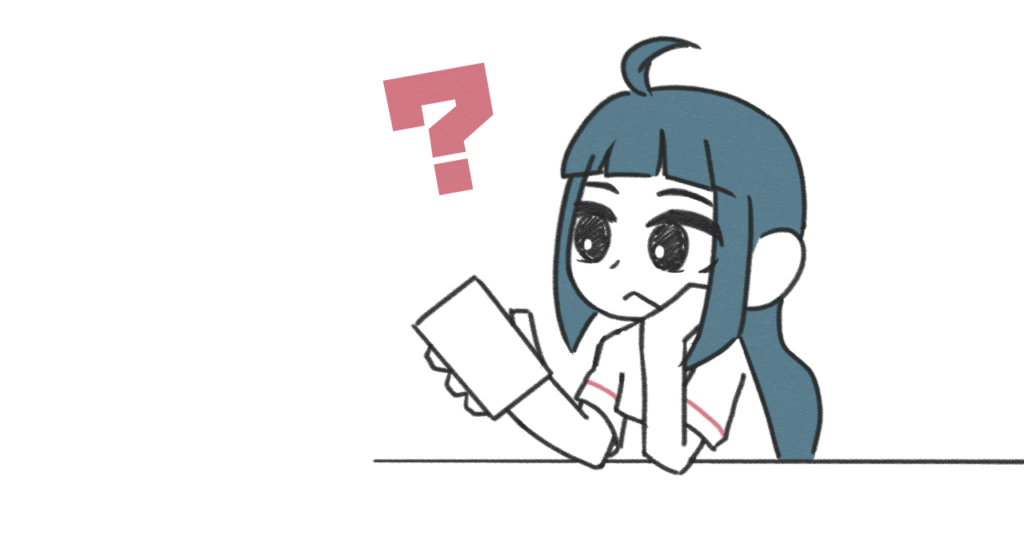
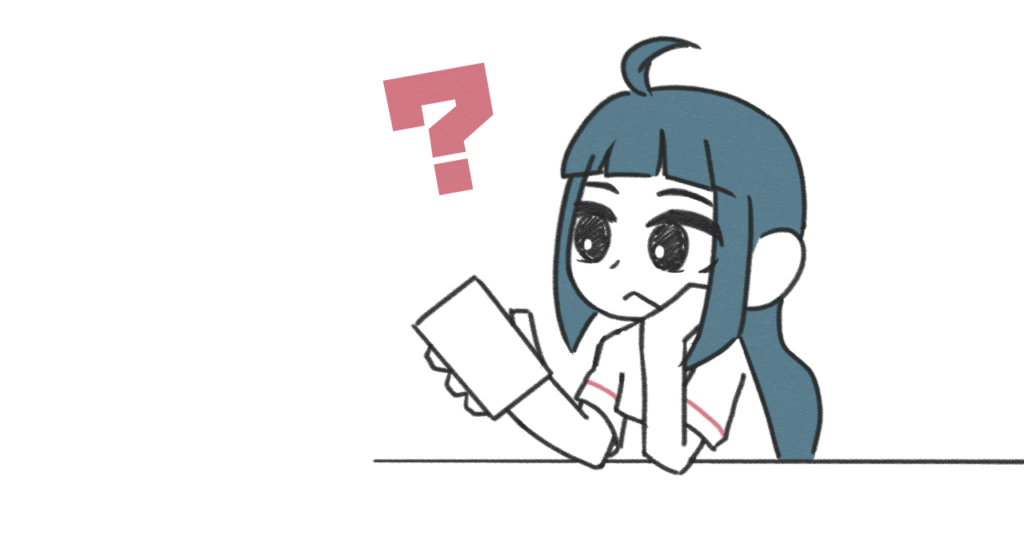
There was a new app on her home screen.
彼女のホーム画面に新しいアプリがあった。
Thereって何のためにあるの?
上記のようなThere構文 は、新しい情報や初めて話すものを紹介するときに使います。
代名詞(youやheなど)を主語にする形、たとえば “There were you” は基本的に使いません。
ただし、”There you were.” のような感情を込めた決まり文句としての用法はあります。
これは「そこにいたんだね」といった感動や発見のニュアンスを伝える特別なケースです。
She didn’t remember downloading it.
彼女はそれをダウンロードしたことを覚えていなかった。
The icon was simple—just a blue circle with white lines inside, like waves or wind.
そのアイコンはシンプルだった―ただの青い丸で、中には波や風のような白い線が入っていた。
No name, no notifications.
名前もない…通知もない…
She hesitantly tapped the icon, driven by curiosity.
彼女は好奇心に駆られて、おそるおそるそのアイコンをタップした。
For a second, nothing happened.
一瞬、何も起こらなかった。
As she wondered what was going on, the screen began to swirl, and Yuki lost consciousness.
不思議に思っていると、画面が渦巻き始め、ユキは意識を失った。
不思議に思っているだけなら what以降はなくてもいいんじゃない?
wondered は、単なる疑問ではなく、「理由や原因を考えたり、不思議に思ったりする気持ち」を表します。
だから何について考えているのかがはっきりしないと、ネイティブは「何を?」と疑問に思います。
それで “what was going on”(何が起きているのか?) の部分が必要になるんです。
次回: ユキが目を覚ます場所は…?
ここまで読んでくださり、ありがとうございました!
次回は、ユキがとある場所で目を覚ましてから物語が動き出します。
どうぞお楽しみに
